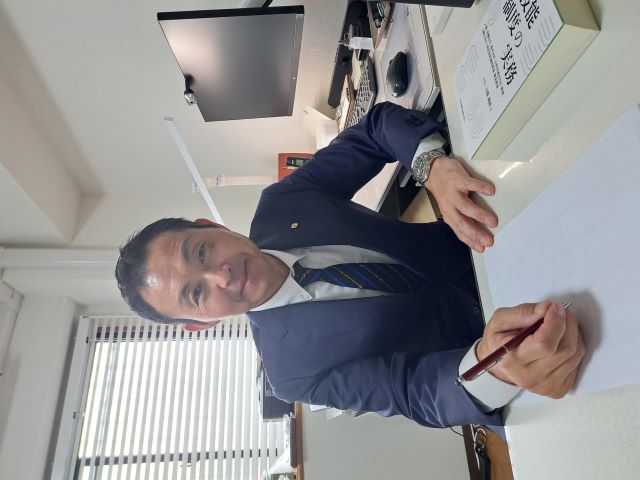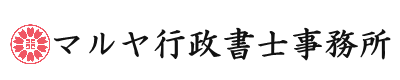一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局 となっています。
新たに運送事業の許可を取得しようとお考えのかたは、許可に関する要件を知り、その要件を満たすことができるかどうかを検討し、申請前の事前準備を行なう必要があります。
また、一般貨物運送事業許可は更新制ではありません。
【運送事業】
1,一般貨物自動車運送事業
2,特定貨物自動車運送事業
3,貨物軽自動車運送事業
このページでは、1,~3,の中の
1,一般貨物自動車運送事業について解説していきます。
(定義)
他人の需要に応じて運賃をもらって自動車(軽自動車及び2輪車を除く)を使用して貨物を運ぶ事業。
特定貨物自動車運送事業以外のもの。貨物自動車運送事業法第2条第2項
緑ナンバー
白ナンバー 比較表
| 貨物自動車運送事業 | 特定貨物自動車運送事業 | |
|
ナンバー |
緑ナンバー | 白ナンバー |
|
有償・無償 |
有償で運ぶ |
有償で運ぶ |
| 社会保険 | 全員加入義務あり |
運送業法上は、 |
| 帳簿作成 |
運転日報、点検記録簿など |
なし |
| 法定点検 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 運行管理者 | 選任する | 選任しない |
1,新規許可申請書に関する記載事項・添付資料の一覧
許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可にはなりません。
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をおこなわれるかたは、
下記の表【新規許可申請書に関する記載事項・添付資料の一覧】のなかにある、申請書類に加え、すべての証明資料を添付又は提示し、事業を営むことにつき、何ら支障がないことを証明しなければ許可を受けることができません。
それでは、こちらで求められている証明資料および内容を細かく見ていきます。
【全体像】
【新規許可申請書に関する記載事項・添付資料の一覧】
|
表紙 事業計画 |
|
| ▼ 以下、記載事項・添付書類 | |
| 運行管理体制 |
・運行管理体制 |
| 資金計画と自己資金 |
・必要資金全体標 ・1回目残高証明日から2回目残高証明日までの通帳コピー |
|
施設概要 |
・周辺地図(営業所と車庫の位置関係図) |
|
車両の使用権原を証する |
・車両購入の場合:売買契約書等 |
| 申請者に関する書類 |
法人の場合 |
|
個人の場合 |
|
|
欠格要件に該当しない旨の |
法人の場合 |
|
個人の場合 |
|
| 利用運送に関する書類 | 運送委託契約書 |
| 委任状 | 行政書士による代理申請の場合 |
さらに添付書類として、
・「事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制」
・「事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理の体制」
・「苦情処理責任者・担当名および各役職等」
・「運送約款の認可」
・「所要資金の見積が適切であることの証明」
を示し、営業するにあたり、準備が整っていることを証明する必要があります。
分かりやすく整理したものが下記の表になりますのでご覧ください。
【事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制】
|
【目次作成】 |
| ▼ 以下、記載事項・添付書類 |
|
1,運行管理及び整備管理の体制 ②役員・必置資格者・従業員 ③運転者 ④アルコール検知器配備計画 |
| ▼ |
|
2,事故防止及び過積載の防止に対する指導教育及び |
| ▼ |
|
3,苦情処理責任者担当者氏名及び |
| ▼ |
|
4,適応する運送約款の認可 |
| ▼ |
|
5,【所要資金の見積】 |
| ▼ |
|
6,資金調達方法及び調達資金の挙証 (2)個人の場合 |
2,ひとに関する要件
➀法令試験への合格
常勤役員となるかたの中から1名が役員法令試験を受験し、合格する必要があります。(他業種兼務役員は受験資格を否定される場合があり、予め相談が必要)
この試験は、1回目が不合格の場合、約2か月後に2回目の再試験が行なわれ、不合格の場合、申請自体を取下げることが法定されている試験です。役員法令試験は、許可を左右するうえ、その試験内容は問題数30問、試験時間50分、合格基準:正答率8割以上と高いため、正確な知識が要求されます。難易度の高いの試験のため、事前の対策が必須となります。
試験がいつ行われるかについてですが、近畿運輸局の場合、貨物は2か月に1回奇数月に実施されています。
偶数月の末日までに受験申請が受付けられた場合、翌月奇数月に受験することができます。
中国運輸局の役員法令試験の実施日は下記の通りとなります。
ホームページ内に法令試験/貨物運行管理者試験対策を掲載しておりますので、ご参考いただければ幸いです。
また、各関係法令の第1条の目的条文も頻出分野となりますので、必ず確認し、試験で何度も出題されている条文は、何を目的に作られた法令なのか答えられるレベルにしてください。
最初は拒絶反応を示すかも知れませんが、見慣れることで覚えられます。これから運送業を営むのであれば、常に法令遵守と輸送の安全の確保が求められますので、目的条文を深く理解しておくことは有意義だと思います。
目的条文第1条
役員法令試験
近畿運輸局
中国運輸局/試験概要
| 貨物運送業/役員法令試験 | |
| 出題範囲 |
➀貨物自動車運送事業法 12/30問 |
| 試験会場 |
近畿運輸局 |
|
中国運輸局 |
|
|
隔月(奇数月)で実施 |
|
| 書籍の持込 |
持込不可 ↑ |
| 設問方式 |
◯✖の正誤方式と |
| 出題数 | 30問 |
| 合格基準 |
正答率80%以上 |
| 試験時間 | 50分 |
|
特例措置 |
なし |
| 合格率 | 60%~75% |
| 過去問等 | |
②欠格事由に該当しないこと
貨物自動車運送事業法第5条に定められており、1,~8,のいずれか1つに該当すれば一般貨物運送事業の許可を受けることは出来ません。
また、トラックGメンによる監査等で「営業自動車の使用停止処分など」の行政処分を受けた場合、別会社を設立し許可を受けることは出来ませんし、法人の役員は常勤役員のほかに非常勤役員を含み、申請法人だけでなく、親会社、子会社、グループ会社が欠格要件に該当する場合も許可されませんので注意が必要となります。
1, 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
禁錮の刑とは
例えば、内乱罪や騒乱罪、公務員が職権を乱用した汚職、名誉毀損、交通事故による過失運転致死傷罪などが禁錮刑の適用対象となります。
2, 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
3, 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
4, 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
5, 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
6, 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
7, 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
8, 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
③運転者5人以上
5人以上の運転者が必要となりますが、兼務禁止規定はありません。よって、常勤役員、常勤の事務員が運転者を兼務することも可能です。
④運行管理者
最低1名以上選任し、配置基準に適合するようにしなければなりません。
【運行管理者の選任数の最低限度】
事業用自動車の車両数/30+1
【運行管理者試験受験資格】
1,2,いずれかに該当していること
1,事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上ある者
2,NASVA自動車事故対策機構等が行う基礎講習修了者
【運行管理者になるには】
➀②ふたつの方法があります。
➀国家試験である、貨物運行管理者試験に合格する。
概要/役員法令試験/貨物運行管理者試験
試験対策/役員法令試験/貨物運行管理者試験
②実務経験選任要件を満たし
申請書と証明書など必要資料を揃え、管轄運輸支局へ提出する。
【実務経験選任要件】
運送業許可等を有する運送事業者のもとで、運行管補助者選任期間が5年以上あり、かつ、その期間にNASVA自動車事故対策機構等が行う基礎講習1回以上、一般講習4回以上(講習の合計5回以上)を受講している者であること。講習ごとに修了証明書が発行されます。
【運行管理者欠格要件】
地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
【運送業許可申請との関係性】
運送業許可申請後、許可取得までに運行管理者試験に合格し、選任されれば要件を満たします。
| 整備管理者との兼任 | できます |
| 運転者との兼任 | できません |
| 運行管理者が補助者も兼任 | できません |
| 2以上営業所を兼任 | できません |
【許可後実務上の規定】
なお運転者に対して行なう点呼について、事業者は補助者を選任することができ、補助者に行なわせる場合であっても3分の1以上は運行管理者が行なわなければなりません。
また、業務に支障がない場合であれば、補助者が同一会社の、他の営業所の補助者を兼務することは可能とされています。
運行管理者が他の営業所の運行管理者を兼務することはできません。
⑤整備管理者
常勤する整備管理者を1名選任しなければなりません。運転者と兼務することは可能ですが、実務を考えた場合、車両故障が発生したときに、対応することができない可能性が高いため、兼務させないことが望ましいとされています。
<整備管理者の資格要件>
また、整備管理者として選任するためには、(1)~(3)のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
【資格要件】
(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
(2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
(3)前2号の要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること(現在、該当するものはありません。)
【資格要件】の解釈は次の通りです。
(1)実務要件での許可申請を行なう場合、下記の解釈が非常に重要となります。
(1)「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
①整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
(2)「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
①整備管理者の経験
②整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
③整備責任者として車両管理業務を行った経験
(3)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
イ)二輪自動車
ロ)二輪自動車以外
の2種類です。
なお、実務経験を積んだ整備工場等で、複数の車種の整備等を行っていた場合には、整備等を行っていた全ての車種に係る実務経験を有しているとみなせることから、その車種に係る整備管理者に関する資格要件を満たすと解せます。
また、選任される事業場で最も多く使用されている自動車に係る実務経験を有していれば、当該事業場に異なる車種の自動車があったとしても、資格要件を満たすと解して差し支えありません。
(4)「地方運輸局長が行う研修」とは、選任前研修をいい、どの運輸支局が実施した選任前研修であっても、また、いつ修了した研修であっても認められます。
3,ものに関する要件
➀営業所
1,用途地域
申請する事業者が、用意しなければならない物のひとつが、営業所です。
広い意味で営業所には➀事務所、②車庫、③整備工場が含まれ、どこでも申請が認められる訳ではありません。ざっと考えただけでも都市計画法、建築基準法、農地法、道路法、消防法などの規制をクリアしなければなりません。例えば、都市計画区域内に➀②③を構え、一般貨物自動車運送事業の許可申請を行なう場合は、①事務所②車庫③整備工場では、許可が認められる用途地域が異なります。
下の二つの表をご参照ください。
【➀運送業事務所・②自動車車庫】と【③自動車整備工場】で用途地域による建築物の用途制限が、異なることがお分かりになると思います。
【➀運送業事務所・②自動車車庫】
【用途地域による建築物の用途制限比較表】
|
用途地域 |
第一種低層 |
第二種低層 |
田園住居 |
第一種中高層 |
第二種中高層 |
第一種 |
第二種 |
準住居地域 |
近隣 |
商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 |
工業 |
用途地域の |
備考 |
|
建築物 |
|||||||||||||||
|
事務所等 (事業所) |
× |
× |
× |
× |
➀ |
② |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
➀床面積が1,500㎡以内で2階以下であること ②床3,000㎡以内であること |
|
兼用住宅で、事務所等として使用する |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
◯ |
兼用住宅とは、住宅の一角を事務所等として利用している場合の |
|
事務所等(事業所)の敷地内にある自動車 |
× | × | × | × | ➀ | ② | ③ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ |
➀自動車車庫の床面積が1,500㎡以内で2階以下であること ②自動車車庫の床面積が3,000㎡以内で2階以下であること ③自動車車庫が2階以下である。ただし、自動車車庫の床面積は |
|
事務所等(事業所)の敷地外で別地に |
× | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲自動車車庫の床面積が300㎡以内で2階以下であること |
|
注釈など |
◯=建てることができる ×=建てられない (注1)用途地域が指定されていない地域を示す。ただし、市街化調整区域は除きます。 (注2)兼用住宅の場合は別途の規制があります。
・建築物を建てるとき、借りるときは、建築基準関係規定に基づく申請・許可が必要な場合があります。 ・あなたが希望する使い方(用途)がその場所でできるのか、構造等は、都市計画法や建築基準法等を みたしているか、必ず建築士などに確認してください。 ・運送業の事務所等は、その場所によっては設けることが出来ない場合や、規模に制約のある場合が あります。 ・屋根と壁、若しくは柱がある、プレハブ・ユニットハウス・コンテナ・DIYの小屋や、土地に定着した トレーラーハウスも建築物の扱いとなりますので、手続が必要です。 ・違反者には都市計画法および建築基準法等の各種法令に基づき、違反指導が行われる場合があります。 (違反すれば法律により罰せられる可能性があります。) ・良好な街づくりのため、都市計画のなかでは土地の利用のルールを決めています。 都市全体を区域さらに地域に分け、それぞれの区域や地域で建てることのできる建築物に関しての 規制を定めています。
・屋根付き車庫である必要はありません。 |
||||||||||||||
【③自動車整備工場】
【用途地域による建築物の用途制限比較表】
|
用途地域 |
第一種低層 |
第二種低層 |
田園住居 |
第一種中高層 |
第二種中高層 |
第一種 |
第二種 |
準住居地域 |
近隣 |
商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 |
工業 |
用途地域の |
備考 |
|
建築物 |
|||||||||||||||
|
自動車の修理工場で、作業場等の床面積≦50㎡ |
× |
× |
× |
× |
× |
▲ |
▲ |
▲ |
▲ |
▲ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
▲使用する機械類に制約があります (コンプレッサー、塗装・金属加工等の機械など) |
|
自動車の修理工場で、作業場等の床面積≦150㎡ |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
▲ |
▲ |
▲ |
◯ | ◯ | × |
◯ |
|
|
自動車の修理工場で、作業場等の床面積≦300㎡ |
× | × | × | × |
× |
× |
× |
× |
▲ |
▲ |
◯ | ◯ | ◯ |
◯ |
|
|
自動車の修理工場で、作業場等の床面積>300㎡ |
× | × | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
注釈など |
◯=建てることができる ×=建てられない ▲=その他の制限あり (注)用途地域が指定されていない地域を示す。ただし、市街化調整区域は除きます。
・建築物を建てるとき、借りるときは、建築基準関係規定に基づく申請・許可が必要な場合があります。 ・あなたが希望する使い方(用途)がその場所でできるのか、構造等は、都市計画法や建築基準法等を みたしているか、必ず建築士などに確認してください。 ・運送業の事務所等は、その場所によっては設けることが出来ない場合や、規模に制約のある場合が あります。 ・屋根と壁、若しくは柱がある、プレハブ・ユニットハウス・コンテナ・DIYの小屋や、土地に定着した トレーラーハウスも建築物の扱いとなりますので、手続が必要です。 ・違反者には都市計画法および建築基準法等の各種法令に基づき、違反指導が行われる場合があります。 (違反すれば法律により罰せられる可能性があります。) ・良好な街づくりのため、都市計画のなかでは土地の利用のルールを決めています。 都市全体を区域さらに地域に分け、それぞれの区域や地域で建てることのできる建築物に関しての 規制を定めています。
|
||||||||||||||
また、農地を農地転用する場合では、農業委員会と協議する必要がありますし、現況のまま農業用倉庫を車庫として利用する場合は、運輸局と協議する必要があります。
都市計画区域内に営業所を設置するときは気を付けてください。原則「市街化調整区域」では許可されません。
2,公共施設などとの距離規制
2019年の一般貨物自動車運送事業法の改正にともない、原則として車庫出入口に関する規制はなくなりました。そのため、近くに小学校や幼稚園があっても運送業許可取得に影響は与えません。
ただし、トラックの出入り口を新設する際は、
①出来るだけ学校施設から離れたところを出入口にする。
②見通しの良いところを優先する。
③運行時の一時停止と安全確認の徹底を怠らないこと。
上記➀~②を基準にして決め、許可後は③を徹底してください。
地元のかたから親しみを持ってもらえるような運送会社を目指しましょう。
3,接道(車庫前面道路)の幅員
結論から言えば、道路の車両幅員が5.5メートル以上であることが必要です。
数式:(5.5メートルー0.5メートル)÷2=2.5メートル ←2.5メートルが車両制限令/保安基準で定められた車幅の上限値
この規定は道路制限令第5条に定められており、一定の数式により答えを導くことができます。
ただし、交通量や一方通行道路であるか否かなどで数式が変わりますので、ご相談をいただければ現地調査させていただきます。
また、実際に道路を通行出来ても、車両が通れるかどうかの判断をするのは道路管理者です。
そして通れることの証明が幅員証明です。
道路管理者である自治体が発行する幅員証明を取得し、車庫の出入口が面した道路が、車両制限令に適合していることを証明するため、許可申請時に添付資料として提出することが義務付けられています。
また、国道が車庫前面道路となる場合は、幅員証明が不要となります。
・道路管理者
(例)市道=◯◯市、県道=〇〇県
・幅員証明
一般貨物自動車運送事業許可においては、車庫の要件を満たしていることを証明するために取得します。
・通行認定
道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係によって通行の制限が生じることがあります。
それらの道路をやむを得ず通行する場合に受ける認定が通行認定と呼ばれ、道路管理者に申請します。
通行認定は許可が下りても許可期間(2年間)があり、同じ車庫と同じ車両の使用を続ける限り更新手続きが必要です。
・幅員証明が発行されない場合
一般貨物自動車運送業の許可申請書類の中にも「幅員証明に代わる添付書類」として定められています。添付書類として定められているものは、
➀メジャー等で計った道路幅員の写真
②計画車両を置いた写真
③宣誓書
➀~③を添付のうえ申請します。
幅員証明が発行されない場合は、自身で支障がないことを証明する必要があります。
【まとめ】
車庫を営業所に併設する場合、離れた場所に確保する場合が考えられますが、国道を除き、幅員証明が出る前面道路に車庫を確保することが、許可取得の近道と言えます。ご検討の際は、自治体にあらかじめ確認されることをお勧めします。
②休憩施設・睡眠施設
1,休憩施設
休憩施設に必要な備品が備えられていることが確認できる写真の添付が求められます。
具体的には、イス、テーブル、ソファー、食事が摂れる設備、トイレ、台所などが挙げられますが、面積要件はありませんので、常識的に考えて休憩が取れると判断出来うる施設となります。
アパートの一室などでも構いません。
2,睡眠施設
睡眠を与える必要がある運行がない場合は、設置する必要がありません。必要がある場合の面積要件は「必要人数×2.5m」の広さを確保する必要があります。寝ることができる環境が整えられていることが前提になりますので、実際はパーテーションで仕切ったり、睡眠用の部屋を設置している事業者が多いです。主たる営業所を登録している場合、共同運行など複数の事業者が同じ睡眠施設を登録することも可能です。
③車両の数5台以上、事業用自動車の構造、使用権原
【車両の数、事業用自動車の構造、使用権原】
| 1 | 営業所毎に配置する自動車の数 |
定める種別ごとに5両以上 ただし、①霊きゅう運送、②一般廃棄物運送、③一般的に需要の少ないと認められる |
貨物自動車運送事業法施行規則 第2条 |
| 2 |
計画する事業用自動車にけん引車 |
けん引車+被けん引車を1両と算定します | 〃 |
| 3 | 事業用自動車 |
1,大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること |
〃 |
④車庫
1,場所の要件
【近畿運輸局管内】
【営業所と車庫の距離規制】
| 国土交通大臣が定める地域 | 国土交通大臣が定める距離 |
|
【滋賀県】 【京都府】 【大阪府】 【兵庫県】 【奈良県】 【和歌山県】 |
10キロメートル |
|
↓※端的に言うと各都府県とも、上段の地域以外の市町村の距離規制がこちらです 【滋賀県】 【京都府】 【大阪府】 【兵庫県】 【奈良県】 【和歌山県】 |
5キロメートル |
【中国運輸局管内】
【営業所と車庫の距離規制】
| 国土交通大臣が定める地域 | 国土交通大臣が定める距離 |
| 中国運輸局管内全域 | 営業所から直線で5キロメートル |
2,車庫の面積
車両制限令
(幅の制限)
第五条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅=(当該道路の車道の幅員ー0.5メートル)÷2
3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。
第六条 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅=当該道路の車道の幅員ー0.5メートル
2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。
3,営業所との距離について
4,前面道路の幅員について
➀下記、保安基準関係の表をご覧ください。車両のサイズは車両制限令第三条1項~5項に定められています。
②長さ、幅、高さについて規定値を超えるものについては、そもそも当該道路を通行することが出来ません。
③特殊車両通行許可(特車)が必要となりますので、ご検討中のかたはご相談ください。
車両制限令/保安基準関係
| 項目 | 保令の要点 |
| 長さ、幅、高さ |
・長さ12m(告示で定めるものにあっては13m) |
| 軸重等 |
自動車の軸重は10tを超えてはならない |
|
原動機 |
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の自動車は、 |
| 車体及び車枠 |
車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める |
| 突入防止装置 | 貨物の運送の用に供する自動車(二輪自動車を除く)の後面には突入防止装置を備え付けなければならない |
| 窓ガラス | 可視光線透過率が70%以上であること |
| 後部反射鏡 | 夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認 できる、反射光の色が赤色の後部反射器を備えなければならない |
| 大型後部反射器 | 車両総重量7t以上のものの後面には、後部反射器+大型後部反射器を備えること |
| 警音器 | 警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定のものであること |
| 非常信号用具 | 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること |
| 停止表示器材 |
夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること |
| 後写鏡 | 自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは衝撃を緩衝できる構造であること |
| 消火器 |
火薬類を運送する自動車、指定数量以上の高圧ガスを運送する自動車及び指定数量以上の危険物を運送する |
|
点滅灯火 |
旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器は可(乗合バス) |
5,使用権原
➀営業所について
・自己所有の場合は登記簿謄本
・借入の場合は契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示が求められます
6,その他に注意しなければならないこと
|
屋根付き車庫の場合は、基本的に都市計画法で定められた「市街化調整区域」と呼ばれる場所では認められない |
|
駐車場出入口が、道路の曲り角や横断歩道から5m以内にないこと |
|
駐車場出入口が、基本的に交差点の角ではないこと |
|
駐車場出入口の前面道路の幅は、道路幅員証明書または道路法に定める車両制限令が取得できる幅があること |
|
事業用車両を停めたとき、車両と車両の間隔が50cm以上確保できる広さがあること |
|
事業用車両を停めたとき、車庫と車両の間に50cm以上の隙間が確保できる広さがあること |
| 駐車場出入口は、路肩に乗り上げることなどなくトラックの出入りができる幅があること |
4,お金に関する要件
➀最低2,500万~3,000万円
| 新規許可申請書に関する記載事項 | 添付資料の一覧 |
| 資金計画と自己資金 |
・必要資金全体標
・車両関係必要資金明細、資金調達方法 ・金融機関の残高証明書、出資金引受書(法人設立時) ・出資者の残高証明書(運輸局による) ・1回目残高証明日から2回目残高証明日までの通帳コピー (運輸局による) |
1,新規許可申請書に関する記載事項・添付資料には、必要資金の全体、具体的な内訳、そして必要資金額を上回る資金残高証明を添えて提出することが定められています。
こちらのページは、必要資金の全体像を示すうえで、なにが、いくらかかり、合計で必要資金をいくら準備しなければならいのか、申請者ごとに異なる必要資金のイメージを掴んでいただくことを目的としています。一般貨物自動車運送業を営むうえで下記➀~⑤に示しているものが代表的なものになりますので、ご自身にあてはめてお考えください。
【許可申請後の注意点】
この必要資金は許可申請後の1回目残高証明日から、申請からおよそ2~3か月後の2回目残高証明日まで、その残高を維持する必要がありますので銀行で融資を受ける場合など、申請後、許可がおりるまでの間に返済が始まり、必要資金を残高が下回ることがないようにしなければなりません。
【資金計画書】
事業開始に要する資金
| 必要額 | ||
| 人件費 | 2ヶ月分 | |
| 燃料油脂費 | 2ヶ月分 | |
| 修繕費等 | 2ヶ月分 | |
| ➀車両 | ||
| 自己所有 | 5台以上の車両が必要です |
分割払いの場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金 |
| リース | 5台以上の車両が必要です |
6ヶ月分の賃借料等 |
| ②建物 | ||
| 自己所有 | 事業所、睡眠、休憩施設、整備工場 |
分割払いの場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金 |
| 賃貸借 | 6ヶ月分の賃借料、敷金等 | |
| ③土地 | ||
| 自己所有 | 事業所、睡眠、休憩施設、整備工場 |
分割払いの場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金 |
| 賃貸借 | 6ヶ月分の賃借料、敷金等 | |
| ④保険料 | ||
| 自賠責 | 1年分 | |
| 任意保険 | 1年分 | |
| ⑤各種税 | ||
| 租税公課 | 1年分 | |
| 登録免許税 | 120,000円 | |
|
(1)資金調達について十分な裏付けがあること |
必要資金額が定まり、法的にも問題がないと判断できれば、いよいよ許可申請手続きの準備に入ります。自己資金に加え、借入れをご検討されるかたも多いと思いますので、当事務所では、助成金、補助金、融資の専門家と提携したご提案をさせていただいております。ご検討されているかたは、お気軽にお声がけください。
私自身、大型自動車第二種免許を持ち、貨物運行管理者、旅客運行管理者、第一種衛生管理者、乙種第四類危険物取扱者の有資格者でもありますので、特定行政書士として「監査指導対策」から、「役員法令試験対策・貨物運行管理者試験対策」、輸送の安全の確保に欠かせない「バス・大型貨物自動車の運転に関する技術的指導」に至るまで一貫したご提案をさせていただきます。どうぞ、宜しくお願い致します。