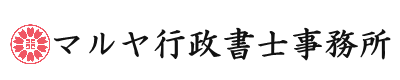【2025年3月現在】
役員法令試験対策
貨物運行管理者試験対策
- 1,【改善基準告示】2024年施行
- 時間についての解釈
- 2,拘束時間の考え方
- 3,事故の報告(届出義務) 事故の速報
- 4,事故報告書と速報(貨物自動車運送事業関係のみ)
- 5,運行管理者の選任数
- 6,事業者と運行管理者の業務
- 7,貨物自動車運送事業の種類
- 8,事業内容に変更が生じたときの、許可・認可・届出
- 9,過労運転防止のために義務付けられていること
- 10,事業者の業務
- 11,運転者に対して行う点呼
- 12,運行管理上、事業者が行なうこと
- 13,記録内容・保存期間等
- 14,特別な指導と適性診断
- 15,運転者の遵守事項
- 16,道交法の規定による自動車
- 17,車両法の規定による自動車
- 18,免許の種類と運転できる自動車の範囲
- 19,車両の各種登録手続き
- 20,手続すべき期間
- 21,自動車車検・検査証票・保安基準関係
- 22,各法律の目的条文
- 23,過去問
1,【改善基準告示】2024年施行
2024年4月より改善基準告示が示され、拘束時間、休息時間、運転時間、休日労働に関する基準が厳格化されました。さらに、トラックGメンによる監査も厳格化されたことにより、国土交通省による、行政指導及び行政処分が全国で激増しています。
物価や人件費、燃料価格高騰も重なり、厳しい状況に立たされている事業者も多いと思いますが、いま事業者には法令の遵守と安全な輸送の確保の徹底が求められています。
このページでは、貨物運送業に関する「役員法令試験」と「貨物運行管理者試験」のポイントをまとめています。法令遵守・輸送の安全の確保の基礎となる部分であり、結果として御社を守ることにも繋がると思いますので、ご参考いただければ幸いです。
時間についての解釈
| 時間の種類 | 解説 |
| 1日の拘束時間 |
・1日の労働時間+休憩時間(仮眠時間含む)=1日の拘束時間 「1日目」始業6:00~終業18:00 「1日目」拘束時間は14時間 「2日目」始業4:00~終業18:00 「2日目」拘束時間は14時間 ・延長する場合でも、最大15時間を超えないこと |
| 労働時間 | 作業時間(運転・整備・荷扱い等)+手持ち時間(荷持ち等)=労働時間 |
| 休息時間 | 勤務(終業)と勤務(始業)のあいだの時間(在宅時間) |
| 2日平均の運転時間 |
2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して1日当たり9時間 |
| 連続運転時間 |
1回10分以上、 |
| 休日労働 | 2週間について1回を超えないこと |
| 1カ月の拘束時間 | 拘束時間/月 | 拘束時間/年 | ||
| 労使協定なし | 284時間以内/月 | 3,300時間以内 | ||
| 労使協定あり |
年6ヶ月まで |
284時間/月超える月が、3か月を超えて連続しないこと | かつ、1か月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満/月となるように努める | 3,400時間以内 |
| 拘束時間/日 |
拘束時間 |
最大拘束時間 |
最大拘束時間 宿泊伴う長距離運送 |
|
| 1日の拘束時間 |
13時間を |
15時間以内 |
16時間以内 |
|
| 基本時間 | 最低在宅時間 | 例外規定 | ||
| 休息時間 | 継続11時間以上与えるよう努める | 継続9時間以上 |
1週間につき、 |
|
| 運転時間 | ||||
|
2日平均の |
➀始業時間から48時間を平均し、1日あたり9時間を超えない |
|||
| 基本時間 | 休息時間 | |||
| 連続運転時間 | 4時間以内 |
4時間以内又は |
||
【実務】
一般貨物自動車運送事業は、実務上あらゆる場面に「時間のルール」が適用されます。1日、2日平均、月、年間など多岐に渡りますし、労使協定の締結の有無によっても「時間のルール」が異なりますので、まずは、1日の拘束時間、休息時間(在宅時間)、運転時間、連続運転時間などが法令に適合しているか確認し、適合していなければ直ちに是正する必要があります。
2,拘束時間の考え方
「労使協定ありのときの拘束時間」
➀1ヶ月の拘束時間は284時間だが、1年のうち6ヶ月まで310時間/月まで延長可能
②1ヶ月の拘束時間が284時間を超える拘束時間が連続可能なのは3か月まで
③1年の拘束時間3,400時間まで延長可能
拘束時間を設定するときは、原則上記➀~③のすべてに適合していなければなりません。
労使協定を結んでいる場合の「合法の場合」・「違法となる場合」を、表にすると次のようになりますのでご覧ください。
▼
労使協定あり 合法の場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年合計 | |
| 拘束時間 | 270 | 275 | 285 | 288 | 295 | 280 | 282 | 279 | 296 | 285 | 285 | 280 | 3,400 |
|
1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下は6ヶ月以下になるため→合法 |
|||||||||||||
・「労使協定ありのときの拘束時間」の➀②③のすべてに違反していないため合法です。
労使協定あり 違法となる場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 拘束時間 | 286 | 270 | 272 | 270 | 302 | 285 | 273 | 290 | 286 | 287 | 290 | 274 | 3,385 |
| 1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下が11月~2月の4ヶ月連続しているため違法 |
1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下が7ヶ月あり違法 |
||||||||||||
・「労使協定ありのときの拘束時間」の②に違反しているため違法となります。
労使協定あり違法となる場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 拘束時間 | 283 | 283 | 283 | 285 | 305 | 281 | 278 | 280 | 291 | 283 | 285 | 283 | 3,420 |
|
1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下は4ヶ月→合法 |
|||||||||||||
・「労使協定ありのときの拘束時間」の③に違反しているため違法となります。
3,事故の報告(届出義務) 事故の速報
| 各号 | 事故の区分 |
届出義務 |
事故の速報 |
| 第1号 | 転覆事故 | 自動車が転覆したもの(路面と35度以上傾斜) | |
| 転落事故 | 自動車が道路外に転落(落差0.5m以上) | ||
| 火災事故 | 自動車または積載物が火災したもの | ||
| 鉄道事故 | 自動車が鉄道車両(路面電車含む)と衝突または接触したもの | ||
| 第2号 | 衝突事故 | 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの | |
| 第3号 | 死傷事故 | 死者または重傷者を生じたもの |
死者2名以上 |
|
【重傷者とは】自賠責施行令第5条第2号3号 |
|||
| 第4号 | 負傷事故 | 10人以上の負傷者を生じたもの | |
| 第5号 | 積載物漏えい事故 | 積載されている危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの | 速報する |
| 第6号 | 落下事故 | 自動車に積載されたコンテナが落下したもの | |
| 第8号 | 法令違反事故 | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの | 速報する |
| 第7号 | 旅客に係る事故 | 省略します | |
| 第9号 | 疾病事故 |
運転者または特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運航を継続することができなくなったもの |
|
| 第10号 | 救護義務違反事故 | 救護義務違反があったもの | |
| 第11号 | 運行不能事故 |
自動車の装置(原動機、動力伝達装置、燃料装置、車輪、車軸、操縦装置など、道路運送車両法第41条1項各号に掲げる装置) |
|
| 第12号 | 車輪脱落事故 |
車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの |
|
| 第13号 | 鉄道障害事故 | 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの | |
| 第14号 | 高速道路障害事故 | 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの | |
| 第15号 |
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の |
4,事故報告書と速報(貨物自動車運送事業関係のみ)
| 報告書 | 自動車事故報告規則に定めるの事故の場合、30日以内に報告書3通を運輸支局長を経由し、国土交通大臣に提出 |
| 速報 | 下記に該当する事故の場合は、24時間以内にできる限り速やかに運輸支局長等に電話等で速報 |
|
1,2人以上の死者を生じたもの |
5,運行管理者の選任数
【事業所(営業所)ごとの選任数】
|
選任数の最低限度=事業用自動車の車両数/30+1 (例) 【許可後実務上の規定】 ※上記の規定により(例)②の場合、点呼執行者のすべてが運行管理者である必要はありません。 |
6,事業者と運行管理者の業務
| 事項 | 事業者 | 運行管理者 | 参考法令(安全規則) | |
| 事業者 | 運行管理者 | |||
| 運転者 | 運転者を選任 |
選任された運転者以外の |
3条1項 | 20条1項➀ |
| 休息・睡眠施設 | 整備・管理・保守 | 管理 | 3条3項 | 20条1項② |
|
勤務時間 |
勤務時間・乗務時間を定める |
勤務時間・乗務時間の範囲内で |
3条4項 | 20条1項③ |
| 酒気帯び | 運行の業務に従事することを禁止 | 3条5項 | 20条1項④ | |
|
疾病・疲労 |
運行の業務に従事することを禁止 | 3条6項 | 20条1項④の2 | |
|
交代運転者 |
長距離運転・夜間運転の交代運転者の配置 | 3条7項 | 20条1項⑤ | |
| 過積載 | 過積載防止の指導・監督 | 4条 | 20条1項⑥ | |
| 貨物の積載 | 適切な積載措置 | 積載方法の指導・監督 | 5条 | 20条1項⑦ |
|
通行の禁止 |
通行の禁止・制限等違反の防止の指導・監督 | 5条の2 | 20条1項⑦の2 | |
| 自動車車庫 |
営業所に併設 |
6条 | ||
| 点呼 | 点呼の実施・記録・保存(1年間) | 7条 | 20条1項⑧ | |
|
アルコール検知器を設置 |
アルコール検知器を |
|||
| 業務記録 | 運転者ごとに業務を記録・保存(1年間) | 8条 | 20条1項⑨ | |
| 運行記録計 |
運行記録計の記録・保存 |
運行記録計の管理・保存 |
9条 | 20条1項⑩ |
|
運行記録計 |
運行記録計使用不能車の |
20条1項⑪ | ||
| 事故の記録 | 事故の記録・保存(3年間) | 9条の2 | 20条1項⑫ | |
| 運行指示書 | 指示書作成・指示・運転者への携行・変更内容の記載・保存(1年間) | 9条の3 | 20条1項⑫の2 | |
| 運転者等台帳 |
運転者等台帳の作成・営業所への据え置き |
9条の5 | 20条1項⑬ | |
| 指導・監督 |
従業員に対する指導・監督 |
10条1項 | 20条1項⑭ | |
| 適性診断 | 惹起、初任、高齢運転者へ適性診断の受診 | 10条2項 | 20条1項⑭の2 | |
| 異常気象 | 異常気象時の乗務員への支持・措置 | 11条 | 20条1項⑮ | |
| 補助者 | 補助者の選任 | 補助者に対する指導・監督 | 18条3項 | 20条1項⑯ |
| 事故の記録 | 事故の報告 |
事故防止対策に基づく |
事業法24条 | 20条1項⑰ |
7,貨物自動車運送事業の種類
| 一般貨物自動車運送事業 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業で |
|
軽貨物 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業。 |
8,事業内容に変更が生じたときの、許可・認可・届出
| 許可 | 一般貨物自動車運送事業を始めるとき |
| 認可 |
運送約款の制定または変更、事業計画の変更 |
| 届出 | 安全管理規定の制定または変更 |
| 事業用自動車に関する変更(種別毎の数など)は、あらかじめ届出る | |
|
軽微な事業計画の変更 |
9,過労運転防止のために義務付けられていること
| 運転者の選任 |
運転者等を常時専任しておく。ただし、 |
| 休憩施設 | 休憩・睡眠施設(寝具等必要な設備が整えられている施設)を整備し、適切に管理、保守する。 |
| 勤務時間及び乗務時間 | 勤務時間及び乗務時間を定める。 |
| 業務の禁止 |
酒気帯び状態の者を運行の業務に従事させない。 |
| 交代運転者の配置 |
長距離または夜間の運行に際し、疲労により安全な運行を継続できないおそれがある時は、あらかじめ、交代運転者を配置 |
| 業務基準の設定 | 特別積み合わせ運送:起点から終点までの距離が100kmを超えるものごとに運行の業務に関する基準を定める。 |
10,事業者の業務
| 運賃及び料金等の掲示 | 主たる事務所、営業所に公衆に見易いように掲示する。 |
| 従業員の指導・監督 | 従業員の指導・監督のための方針の策定及び措置を講じる。 |
| 点検基準の作成 | 事業用自動車の使用条件を考慮し、定期に行なう点検基準を作成する。 |
| 車庫の位置 | 事業用自動車を保管する車庫を営業所に併設する。 |
11,運転者に対して行う点呼
| 業務前点呼 |
対面又は対面と同等の効果を有するものとして、国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)で行う。 ➀運転者に対しては、酒気帯びの有無 |
| 業務後点呼 |
対面又は対面と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)で行う。 ➀事業用自動車の状況 |
| 中間点呼 |
業務前、業務後の点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で ➀酒気帯びの有無 |
| 酒気帯びの有無についての確認はアルコール検知器(営業所に備えられたものに限る)により行なう。 | |
| 補助者に行なわせる場合であっても3分の1以上は運行管理者が行なう。 | |
| 酒気帯びの状態とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わない。 | |
12,運行管理上、事業者が行なうこと
| 必要な権限の委譲 | 運行管理者に対し、業務を行なうために必要な権限を与える。 |
| 助言の尊重 |
運行管理者が業務として行なう助言を尊重する。また、運転者等は、 |
| 運行管理規定 | 運行管理者の職務及び権限等に関する運行管理規定を定める。 |
| 指導及び監督 |
運行管理者に対し、業務の的確な処理及び運行管理規定の遵守につい |
| 講習➀ |
新たに選任した運行管理者に国土交通大臣の認定を受けた講習※を受けさせる。 |
| 講習② | 事故を起こした営業所の運行管理者に事故の日から1年以内に特別講習を受講させる。 |
13,記録内容・保存期間等
| 業務の記録 |
➀業務開始と業務終了地点、日時、主な経過地点と運行の業務に従事した距離 |
| 運行記録計 |
➀車両総重量7t以上又は最大積載量4t以上の事業用自動車の乗務については運行記録計により、 |
| 運行指示書 |
➀運転者に携行させる。また、運行途中に変更が生じた場合は運転者が携行している運行指示書にも変更内容を記載させる |
| 運転者台帳 |
➀運転免許証の番号と有効期限、年月日及び種類等 |
14,特別な指導と適性診断
特別な指導
| 運転者 | 指導内容 | 指導するタイミング |
| 事故惹起者 |
・惹起運転者の定義 |
再度乗務する前に6時間以上 |
| 初任者 |
運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、運行の安全を |
初めて乗務する前に15時間以上やむを得ない事情があるときは、再度乗務後1カ月以内 |
| 安全運転の実技:20時間以上 | ||
| 高齢者 | 指導時間は設けられていません。適性診断の結果により、運転者自らが考えるように指導すること | 適性診断の結果後1カ月以内 |
適性診断
| 運転者 | 受診要件 | 受診時期 |
| 事故惹起者 |
➀死傷事故を起こし、当該事故前1年間に交通事故を引き起こした者 |
再度乗務する前に |
| 初任者 | 初めて乗務する前3年間に初任運転者の適性診断を受診していない者 |
初めて乗務する前に |
| 高齢者 | 満65歳の運転者 |
満65歳に達した以後、1年以内に1回、 |
15,運転者の遵守事項
運転者の遵守事項
| 疾病、疲労、睡眠不足等により、安全な運行ができないおそれがあるときは、事業者に申し出る |
|
他の運転者等と交替して乗務を開始するときは、他の運転者等から通告を受け、事業用自動車の |
|
運行指示書の作成を要する運行では、運行指示書を携行し、運行の途中で記載事項に変更があった |
16,道交法の規定による自動車
| 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 |
| 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 |
| 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | ━ |
17,車両法の規定による自動車
| 普通自動車 | 小型自動車 |
| 軽自動車 | 大型特殊自動車 |
| 小型特殊自動車 | ━ |
18,免許の種類と運転できる自動車の範囲
| 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 | |
| 車両総重量 | 3.5t未満 | 3.5t以上7.5t未満 | 7.5t以上11t未満 | 11t以上 |
| 最大積載量 | 2t未満 | 2t以上4.5t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
| 普通自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 準中型自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 中型自動車 | ◯ | ◯ | ||
| 大型自動車 | ◯ |
19,車両の各種登録手続き
| 登録の種類 | 手続が必要なとき | 申請者 |
| 変更登録 |
型式、車台番号、所有者の氏名、使用の本拠の位置などを |
所有者 |
| 移転登録 | 所有者を変更したとき | 新所有者 |
| 永久抹消登録 | 自動車が滅失、解体、又は用途を廃止したとき | 所有者 |
| 一時抹消登録 |
自動車が滅失、解体、又は用途を廃止したとき |
所有者 |
20,手続すべき期間
| 15日以内 |
変更登録、移転登録、永久抹消登録、一時抹消登録 |
| 5日以内 | 臨時運行許可証の返納 |
21,自動車車検・検査証票・保安基準関係
自動車の検査の種類
| 1,新規検査 | 2,継続検査 | 3,臨時検査 | 4,構造等変更検査 | 5,予備検査 |
車検証の有効期間
| 自動車の種類 | 初回 | 2回目以降 |
|
車両総重量8t以上の |
1年 | 1年 |
|
車両総重量8t未満の |
2年 | 1年 |
自動車検査証・検査標章に関する規定
| 自動車車検証は当該自動車に常時備え付けておかなければならない |
|
有効な保安基準適合証、予備検査証を自動車に表示している場合は、自動車車検証の交付、備え付け及び検査標章の |
| 検査標章は、自動車検査証が効力を失ったとき、検査証の返付を受けることができなかったときは表示してはならない。 |
| 検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難になったときは、再交付を受けることができる。 |
車両制限令/保安基準関係
| 項目 | 保冷の要点 |
| 長さ、幅、高さ |
・長さ12m(告示で定めるものにあっては13m) |
| 軸重等 |
自動車の軸重は10tを超えてはならない |
|
原動機 |
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の自動車は、 |
| 車体及び車枠 |
車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める |
| 突入防止装置 | 貨物の運送の用に供する自動車(二輪自動車を除く)の後面には突入防止装置を備え付けなければならない |
| 窓ガラス | 可視光線透過率が70%以上であること |
| 後部反射鏡 | 夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる、反射光の色が赤色の後部反射器を備えなければならない |
| 大型後部反射器 | 車両総重量7t以上のものの後面には、後部反射器+大型後部反射器を備えること |
| 警音器 | 警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定のものであること |
| 非常信号用具 | 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること |
| 停止表示器材 |
夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること |
| 後写鏡 | 自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは衝撃を緩衝できる構造であること |
| 消火器 |
火薬類を運送する自動車、指定数量以上の高圧ガスを運送する自動車及び指定数量以上の危険物を運送する |
|
点滅灯火 |
旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器は可(乗合バス) |
22,各法律の目的条文
【貨物自動車運送事業法第1条】
|
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的な |
【道路車両運送法第1条】
|
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証を |
【道路交通法第1条】
|
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資す |
【労働基準法第1条】
|
1,労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための 2,この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるか |
23,過去問
近畿運輸局/一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験/過去問
中国運輸局/一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験/過去問